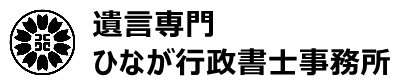⑤事業をきちんとお子様に承継させたいケース
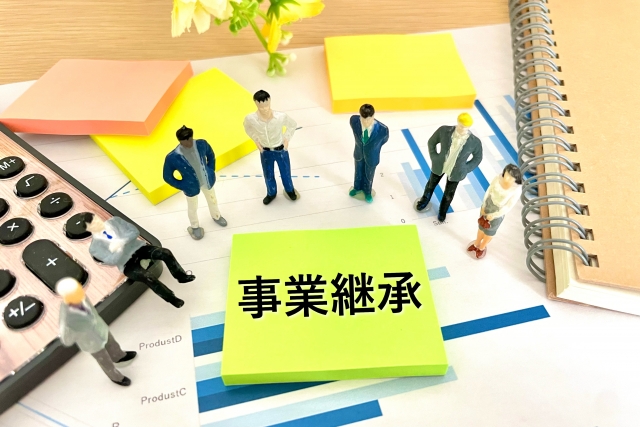
お客様が事業をご経営され、または、農業をされている場合は、これらの跡を継ぐお子様に経営資源となる財産を相続させる必要がありますので、遺言書の作成をおすすめします。
相続、遺贈の場合、農地法3条の許可は不要となります。
借地権、借家権を相続させる場合、賃貸人の承諾は不要です(遺贈の場合は必要)。
遺言書は他のご家族の遺留分(法律上最低限保証された相続分)に留意された内容をおすすめします。
【遺留分侵害が避けられない場合の予防対策】
①生命保険の加入
遺留分を確保する方法として生命保険への加入があります。
例えば、ご長男に事業を承継させる場合、弟姉妹からの遺留分侵害額請求に備えて、受取人をご長男とする生命保険に加入しておきます。死亡保険金は相続財産になりませんので、ご長男が単独でお受け取りでき、この死亡保険金により遺留分侵害額を支払うことができます。この例ではご長男以外の弟姉妹を受取人にしてしまうと、相続財産ではありませんので、遺留分侵害額を請求されていまいますので、ご注意願います。
②早めの生前贈与
他の相続人からの遺留分侵害額請求の予防対策として、早めの生前贈与が考えられます。相続開始の10年より前に行われた生前贈与は原則として遺留分請求の対象にはなりません。
③遺留分の事前放棄の申請
相続開始前の遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は、遺留分の事前放棄が自由意思によりなされたか、必要性があるか、放棄の代償があるか等により許可の有無を判断します。
④付言事項の活用
遺留分侵害額請求権の行使を控えるように、ご遺族が納得できるように理由を記載してお願いします。できましたら、その理由の客観的事実を記載することをおススメします。
一方、遺言書を残さないと、残されたご家族の中で遺産分割協議をしなければなりません。
財産の多寡に関わらず、遺産分割協議はお互いの利益が衝突して揉めることが多いのです。
遺言案をお子様にお伝えずに作成すると、後々お子様の間で揉め事が起きてしまう可能性がありますので、遺言案はお子様にお伝えしてから作成することをおすすめします。