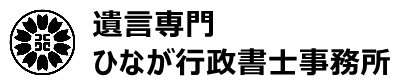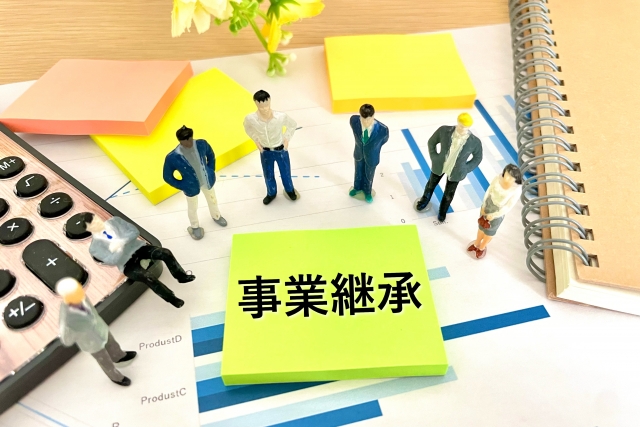③配偶者様の老後を守りたい

私の父が亡くなった時、母は脳梗塞のため入院中であり、母不在の中、
兄弟姉妹で今後のことを相談しましたが、相続トラブルとなりました。
多くはない財産でしたので、私は母の老後のために父の全ての財産を母に相続させて、
母が亡くなった後に、兄弟姉妹で仲良く等分に相続しようと提案しましたが、
その提案は兄弟姉妹には受け入れて貰えませんでした。
配偶者様の老後を守るために
「私の有する一切の財産を配偶者に相続させる」
という遺言書を作成する方法が考えられます。
この場合、遺言書の付言の中で子どもたちに配偶者様への遺留分※侵害額請求をしないようにお願いしておきます。
※法律上最低限保証された相続分(法定相続分の2分の1の財産)
【配偶者居住権】
相続財産の大半を居住用の不動産が占めている場合には、遺言で配偶者様に居住用不動産を相続させると、他の相続人の相続分との関係で金融資産を受け取ることができなかったり、他の相続人が配偶者様に遺留分※侵害額を請求するかもしれません。
その対策として配偶者様の終生の住まいを確保するために配偶者居住権を遺贈する方法があります。
建物を居住権と負担のついた所有権に分けることにより、所有権が100%である場合の時価に比べて、居住権の時価は低くなります。
配偶者の方は居住を終生継続できる上に、居住権の時価が低くなった分、相続分として預貯金等を受け取る方法が考えられます。
ただし、配偶者様が高齢者施設への入所を望んでいる場合、または、将来マンション等への住み替えをお考えになられている場合には配偶者居住権の遺贈はおススメしません。
配偶者居住権を売却して資金を調達することができないためです。なお、居住建物所有者の了解を得て賃貸することで賃料収入を得ることはできます。
配偶者居住権の登記は配偶者様とお子様(住まいの負担付き所有権を有する相続人)と共同して行う必要があります。配偶者様とお子様との折り合いが悪く、共同しての登記が難しい場合は遺言にて遺言執行者を指定されることをおススメします。遺言執行者は配偶者居住権の登記を単独で行うことができます。
遺言案をお子様にお伝えずに作成すると、後々お子様の間で揉め事が起きてしまう可能性がありますので、遺言案はお子様にお伝えしてから作成することをおすすめします。
【負担付相続】
配偶者様がお一人でも安全、安心に生活できるように、負担付相続を遺言書に書かれた方が良い場合があります。
例えば、「遺言者の一切の財産を相続させることの負担として、遺言者の妻が死亡するまで同人を扶養・介護しなければならない。」と記載します。
【貴方と配偶者の老後の安心設計のための遺言信託公正証書】
貴方と配偶者様の老後がご心配な場合に、
例えば、信頼のおける長女を受託者として、貴方と配偶者様の生涯の面倒をみてもらい、
貴方と配偶者様がお亡くなりになられた場合は、
残存財産受益者の長女に信託財産を帰属させることとした遺言信託が考えられます。